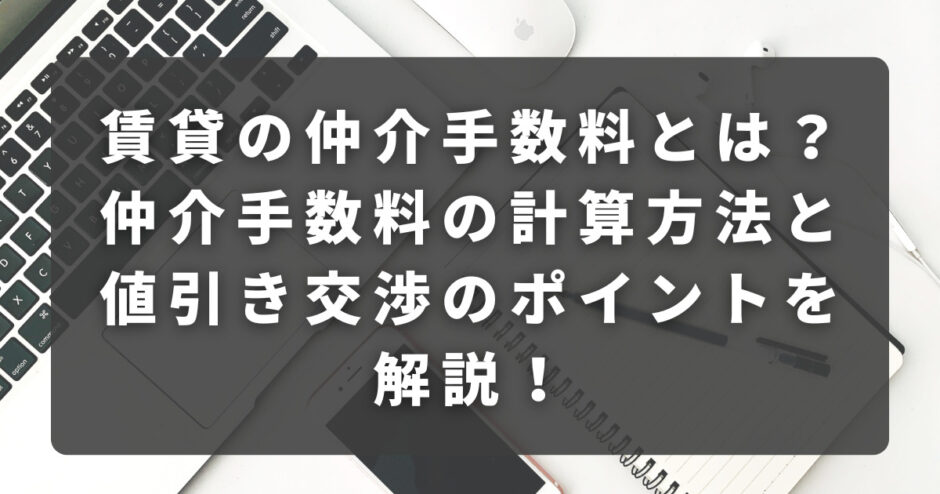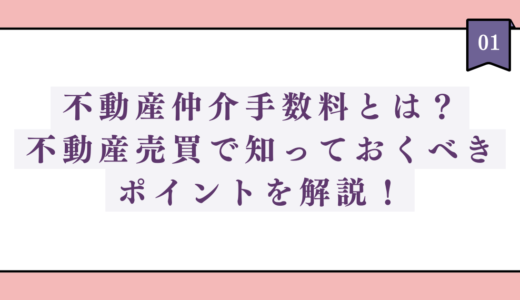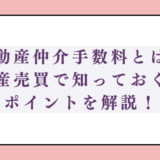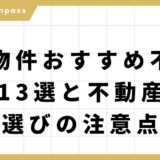こんな悩みを解決できる記事を書きました!
現在では、不動産に関する悩みを解決する記事を提供しています!!
アパートなどの賃貸物件を契約するときには、仲介手数料がかかります。
賃貸物件で契約するときに、敷金・礼金の項目があるので聞いたことはある人も多いでしょうが、仲介手数料という言葉はなじみがない方もいらっしゃるかもしれません。
不動産に限らずですが、世の中には知らないと損をすることはたくさんあります。
この記事では、仲介手数料の相場や仕組み・仲介手数料を抑える場合の方法や注意点などを解説します。
初期費用を少しでも抑えたいという方・損をしたくない!という方はぜひ参考にしてください。
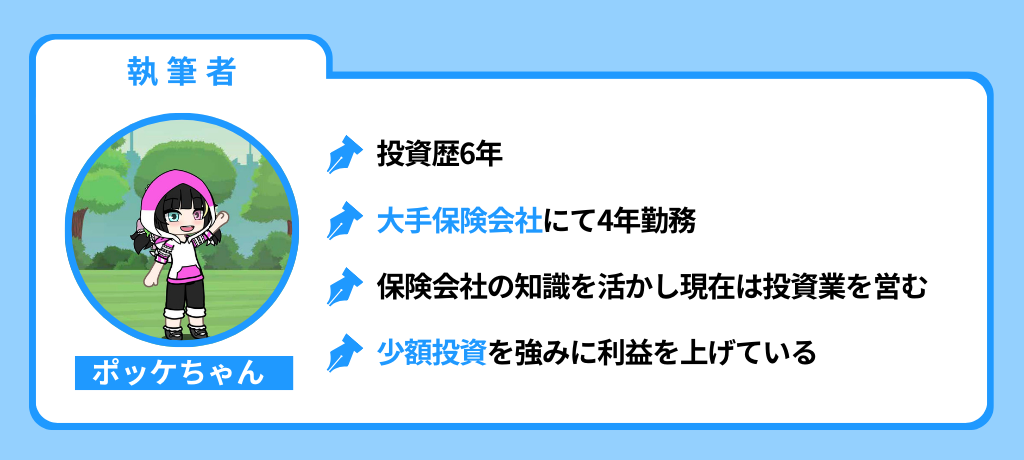

このプロフィールは2025年現在のものです!
目次
仲介手数料とは
不動産の仲介手数料とは、不動産を賃貸契約などを行う際に不動産に依頼する費用であり、賃貸契約を成立してくれた不動産会社に対する成功報酬であると言えます。
不動産などで賃貸契約を行う際は、法律の知識がないとトラブルに発展することもあり、各種サポートも含めて不動産会社に依頼することでトラブルを未然に防げるため不動産会社に依頼するケースが多いのです。
具体的なサポート内容は、貸主と借主の間での仲介役・部屋探し・内件・場合によっては契約条件の交渉・契約内容の説明・契約の締結など多岐にわたります。
このように、個人では難しい内容を代理で行うことで契約をスムーズに行い、その報酬として仲介手数料が発生します。
仲介手数料の仕組みとは
仲介手数料は、不動産会社の収入源の1つです。
不動産会社は、賃貸契約を結ぶために各種サポートを行いその時の費用と、契約を結んだ時の成功報酬として仲介手数料をもらいます。それが不動産会社の収入源の1つとなります。
- 仲介手数料は成功報酬なので、契約が成立しなければ仲介手数料は入らない
- 基本的に貸主・借主それぞれ0.5カ月分+消費税となり合計で1カ月+消費税となり、一方から受け取れる仲介手数料は家賃の0.5ヶ月分で、それを超すのは違法となる(宅地建物取引業法)
- 例外として貸主と借主の承諾を得ている場合は、どちらか一方が全額負担することも可能(契約書に明記しており、契約した場合に有効)
このように仲介手数料の仕組みは、貸主と借主で0.5ヶ月分+消費税を負担し、成功報酬として不動産会社に支払う形になっています。
仲介手数料を支払うタイミングとは
仲介手数料は、賃貸契約を成立してくれたことに対する成功報酬なので、賃貸契約が完了した後に支払われます。
具体的には以下の内容です。
- 仲介手数料は、賃貸契約時の初期費用に含まれており、タイミング的には約3週間後程度(入居審査約2週間・本契約1週間程度)で請求される
- 締結されてから請求が可能なので、原則は締結終了後に請求されるが、場合によっては契約締結前に入金するケースもあり、契約がキャンセルになれば返金される
- 共益費・管理費・駐車場代は含まれないため、賃料が15万円なら仲介手数料は15万円になり、共益費・管理費・駐車場代などを含まれた分を請求された場合は違法となる
上記の通り仲介手数料は賃貸契約終了後に請求が可能であり、初期費用に含まれて請求されます。
仲介手数料の相場は?
宅地建物取引業法により、賃貸物件の仲介手数料は、「賃料1カ月分+消費税」が上限であり、貸主・借主の両方から仲介手数料を受け取る場合は「賃料0.5カ月分+消費税」が上限となります。


仲介手数料の下限の決まりはないので、0.5ヶ月分を下回ることもありますよ!
上限額が「賃料1カ月分+消費税」なので、多くの場合は貸主・借主の両方から仲介手数料を受け取る「賃料0.5カ月分+消費税」である。
例えば家賃が10万円なら消費税込みで11万円・15万円なら消費税込みで16.5万円の計算になります。
※引用元:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」
仲介手数料早見表
| 家賃 | 仲介手数料(0.5ヶ月分) | 仲介手数料(1ヶ月分) |
|---|---|---|
| 5万円 | 27.500円 | 55.000円 |
| 7万円 | 38.500円 | 77.000円 |
| 10万円 | 55.000円 | 110.000円 |
| 15万円 | 82.500円 | 165.000円 |
| 20万円 | 110.000円 | 220.000円 |
※消費税込み(10%で計算)
なお、片方から1ヶ月分請求する場合は、必ず事前に了承を得ている場合に限ります。了承を得ずに0.5ヶ月分を請求すると違法でるある可能性があるので、金額を計算して0.5ヶ月分を超えている場合は不動産に確認しましょう。
令和6年7月1日の法改正により、長期空き家の賃貸借については「1ヶ月分の家賃×2.2倍(税込)」で請求することが可能になっています。
この場合の空き家とは、1年以上居住者が不在の場合を指し、将来にわたり居住や事業などで使われる見込みがないなどの物件を指します。
貸主に対して仲介手数料を上乗せすることになり、借主の負担は改正以前と変わりません。
このように原則仲介手数料は、「賃料0.5カ月分+消費税」であり、事前に了承を得ている場合は「賃料1カ月分+消費税」が可能になります。
1ヶ月を越える請求は、貸主・借主の負担する側の書面により了承を得る必要があり、了承していないにもかかわらず請求がきた場合は、違法であるる可能性がありますので注意して下さい。
仲介手数料を抑える場合の例とは
ここからは、不動産の仲介手数料を抑える5つのケースを紹介します。
不動産会社が直接物件を管理している場合
不動産会社が直接管理をしている物件は、家賃や管理委託料などを得ることが可能なため、不動産の仲介手数料を安く設定できる可能性があります。
自社物件なので仲介業務が不要なため仲介手数料が発生しないので、不動産会社側としても早く契約できるメリットもあるためです。
- 賃貸物件は不動産会社が直接管理する【自社物件】と、貸主から委託される【管理物件】があり、自社物件の場合は直接管理しているため仲介手数料がかからないため半額や無料のケースがある
- 清掃などの管理業務を代行した場合は、貸主から対価を得ることで収益面も確保されてるので仲介手数料値を値引きするケースがある
賃貸物件は不動産会社が直接管理する【自社物件】の場合は値引きがされやすいが、貸主から委託される【管理物件】は仲介手数料が収入源の1つであるため割引は難しくなってしまいます。
直接借主と契約する場合
直接、貸主と契約する場合は仲介手数料を抑えることができる可能性があります。
ですが、不動産会社を介さないため手数料は発生しませんが、賃貸契約の内容に不備があった場合、トラブルが発生するリスクがあるので注意が必要です。
具体的には以下のトラブルが考えられます。
- 敷金・礼金がない分、物件の管理状態が悪い
- 本来ついているような設備かない(クーラーやストーブなど)
- 原状回復義務が曖昧な場合がある
- 家賃が周りより高い可能性がある


原状回復義務とは、退去時部屋の状態が入居時の状態にするための義務です。生活する際に日常的な傷は請求されることは少ないですが、タバコのヤニや掃除すれば奇麗にできるカビなどは、請求される可能性があります。退去時には清掃できる部分に関してはした方がよいでしょう。
直接貸主と契約する場合は、仲介手数料が安くできる可能性はありますが、プロを間に挟んでいないためトラブルに発展することもあるので、直接契約しているケースは多くないでししょう。
入居者を積極的に募集している場合
貸主が入居者を積極的に募集している場合は、不動産仲介手数料を貸主側が負担してくれるケースもあります。
貸主がなるべく早めに空室を解消し収入を得たいため、入居者が本来払う分の手数料を貸主が負担し、入居を決めて欲しいからです。
不動産業界では一般的に引越しの多い【繁忙期】と引越しが少ない【閑散期】があります。
- 【繁忙期】1~3月頃
- 【閑散期】7~8月頃・11~12月頃
この閑散期は、不動産仲介手数料を安くできる可能性が高くなります。
貸主が入居者を積極的に募集している場合(閑散期など)は、入居を早く決めたい貸主が不動産仲介手数料を負担してくれる可能性があるため、仲介手数料を抑えることができます。
ただし、理由が閑散期などで早く入居して欲しいなどの理由で仲介手数料を負担してくれている場合もありますが、別に原因があり安くしている可能性もありますので、よく精査する必要があります。
仲介手数料の半額や無料を行っている場合
仲介手数料の半額や無料を行っている場合も仲介手数料を抑えることができます。
- 不動産会社が早期の空き室解消を目指などの理由で、仲介手数料を下げているので、さらに下げる余地があるから
- 集客力向上、早期の取引成立、他の収益源の確保、そして自社物件の取り扱いといった戦略的動機などが背景にあるから
- より多くの取引を成立させることで自社の利益に繋がるから
競合の多い地域などでは、早く成立させることで顧客の関心を上げ、他の物件の回転率もよくなるので半額や無料キャンペーンを行うことも多いので、そこを狙ってみるのも1つの手段です。
仲介手数料以外に広告費を不動産会社がもらっている場合
不動産会社が仲介手数料以外の報酬を受け取る場合、広告費などを貸主からもらっていることがあり、借主側の仲介手数料を抑えることができる場合があります。
なぜなら、貸主から不動産会社は仲介手数料+広告費をもらい利益を得ているので、借主側の仲介手数料を低くすることができるです。
・貸主側 仲介手数料 5万円(1ヶ月を10万円と仮定) 広告費 20万円(一般的な相場が01~2ヶ月と言われているから)
・借主側 仲介手数料 3万円(仲介手数料に下限はないので)
広告費をもらい仲介手数料を安くできるのは、大家が許可している場合のみなので、物件探しの際に確認するのも手段である(物件の図面資料マイソクにAD〇〇と記載されている場合が多い AD100なら1ヶ月・AD200なら2ヶ月分と考える)
仲介手数料を値下げ交渉するポイント
ここからは、仲介手数料を下げやすいパターンの不動産を紹介します。
仲介手数料を安く設定している不動産会社を選ぶ
仲介手数料を最初から低く設定している物件は、貸主が早く入居者を決めたい可能性があるので、値下げ交渉をする余地があります。
具体的には、期間限定の値引き(閑散期など)や、不動産の激戦区などは顧客を得るため要望が通る可能性があります。
しかし、無理な要求は逆効果になることもあるので注意が必要です。
不動産会社が直接管理している物件を狙う
自社物件なので、仲介手数料は発生しなくても管理業務で収益を上げることができるため、仲介手数料を無料にしてくれる可能性があります。
しかし、その分駐車場代や管理費などで請求されるか可能性がありますので、毎月家賃と駐車場代、管理費を合わせて合計値を考えましょう。
- 仲介手数料が無料 家賃7万円・駐車場、管理費3万円のA物件
- 仲介手数料が3万5千円 家賃7万円・駐車場、管理費1万円のB物件
物件Aは仲介手数料はかかりませんが、毎月10万円支払うのに対し、物件Bは最初に仲介手数料は発生しますが、毎月8万円で済みます。この場合どちらがお得かは一目瞭然です。
このように、賃貸物件を探す際はこのような仕組みを理解しておく必要があります。
仲介手数料の値引き交渉で知っておくべきこと
仲介手数料を値引き交渉する前に仕組み知っておくことで、無理な要求をせずにスムーズに交渉することができます。
ここからは、仲介手数料の仕組みと値引き交渉のポイントを解説します。
基本的には仲介手数料は一律で設定されている
基本的に不動産仲介手数料は一律です。
宅地建物取引業法により仲介手数料の上限があり、その上限が1ヶ月であるため、(場合によっては2カ月の場合もある)貸主と借主の合わせて【1ヶ月+消費税】となります。
原則は貸主0.5か月分・借主0.5か月分なので、仲介手数料は0.5ヶ月分でお得です!などとと表記されていても、特別安くしているわけではないので、このような場合は最初から値下げする可能性も低く、信用性が低い可能性があり、避けるべきでしょう。
福利厚生サービスを利用することで値引きできる場合もある
勤務先の会社が提携している不動産会社なら、福利厚生の一環として社員向けの割引制度があれば値引きされることがあります。
勤務先の福利厚生ページの確認や福利厚生ページを確認し、不動産仲介に関連する特典を探してみましょう。不動産仲介に関連する特典を探しあれば、仲介手数料を値下げできる可能性があります。
物件によって値引き交渉は可能だが難しい
不動産仲介手数料とは、不動産会社に対する成功報酬なので物件の状態で値下げ交渉するのは難しいでしょう。
駅から遠いとか築年数が古い・病院が少ないとかは仲介手数料でなく、貸主との家賃や敷金・礼金の交渉材料であるからです。
仲介手数料を値引くことで起きるデメリットと注意するポイント
ここからは、仲介手数料を値引きすることで起こりえるデメリットと注意するポイントを紹介します。
選択できる物件が少なくなる可能性がある
仲介手数料は不動産会社の収入源の1つなので、仲介手数料を値引きできる物件の数は多くない可能性があり、紹介できる物件が限られてしまうデメリットがあります。
- 不動産会社の自社物件である場合
- 広告費(AD)が出ている場合
- 貸主が積極的に募集をかけている場合
仲介手数料を値引きするには、それ以外で不動産会社にメリットがある条件が必要なため(物件の管理費が別に入るやAD収入があるなど)それがなければ値引きが難しいため、紹介できる物件の数は限られてしまうため選択の幅が狭まってしまいます。
他の希望者がいた場合優先される可能性がある
値下げ交渉する客より、不動産会社が提示する条件の客と契約する方がメリットがあるため、不動産会社が提示する条件で申込があれば、そちらが優先されて先に契約されてしまう可能性があります。
例えば、本来であれば貸主0.5・借主0.5で1ヶ月分の家賃の仲介手数料が入るのが、貸主0.5・借主0.3で0.8ヶ月分の仲介手数料だと不動産会社のメリットが減ってしまいます。
・貸主5万円・借主5万円 計10万円
・貸主5万円・借主3万円 計8万円
→2万円の差がででしまう
不動産会社も利益が出る方の客を選ぶので、値引き交渉する客より提示する条件で契約する客を選ぶ可能性が高いでしょう。ですので好条件の物件は競争率も高いので、無理に値引き交渉するよりも早めの契約をする方が良いかもしれません。
家賃設定が高くなっているケース
中には仲介手数料が無料・又は他より安い物件もありますが、家賃や他の経費の部分もみる必要があります。
- A社 家賃10万円 仲介手数料 無料 管理費1万円
- B社 家賃6万円 仲介手数料 6万円 管理費1万円
どちらが安いかは見比べるとB社ということが分かります。
一見すると仲介手数料が無料なのでお得に見えますが、家賃や管理費で上乗せして最終的に高い金額になってしまいます。
このように、仲介手数料が無料でも、家賃や管理費などで上乗せして高くなるケースがあります。
仲介手数料が低くても他で請求されるケース
上記と似ている部分もありますが、仲介手数料が安くても他で請求されるケースもあります。
具体的には、書類作成費用や事務手数料などで金額請求される可能性があるでしょう。
仲介手数料だけを見るのではなく、経費全体でみて総合的にどちらが金額が低いかを確認して下さい。
仲介手数料が低い場合、その分品質に影響されるケースもある
仲介手数料は不動産会社に対する報酬なので、安く交渉すると紹介される物件にも影響する可能性があります。
(ただし、不動産会社が自ら仲介手数料を下げて入居者を募集しているなどのケースは別です。あくまでも借主側が無理な値下げ交渉する時に可能性があります)
例えば仲介手数料を5万円の物件を探す時に、値下げ交渉をして仲介手数料を3万円で物件を探すとなると、どうしても2万円に下げる所を探すので、その分5万円の物件より質は落ちてしまいます。
このように、値下げすればそれにあった物件になる可能性は当然あります。
入居者が集まらないのには理由がる
一見すると好条件に見えても、いつまでも入居者が集まらないのには理由がある場合があります。
具体的には以下の内容などが考えられます。
- 近隣トラブルが多い
- 利便性が良くない
- 事故物件(告知義務は事件が起きてから1人目の入居者だけだから分からない)だった場合
- 家賃以外にもお金がかかるとか(他より光熱費が高いとか)
このように好条件に見えても、入居者が集まらないのには理由があるのでよく確認してください。
よくある仲介手数料に関する質問
ここからは、仲介手数料に関する質問にお答えします。
仲介手数料に消費税は発生するのか?
消費税法によりサービスは課税対象になるため、仲介手数料には消費税は発生してしまいます。
仲介手数料は不動産会社が事業として対価を得るためのサービスと考えられ、鍵の交換やハウスクリーニングなども消費税の対象になります。
ただし、家賃や管理費・共益費などは非課税とされています。
いつ仲介手数料を払えばいいのか?
仲介手数料は契約が成立した際に発生しますので、入居日までには支払わないとならないといけません。
内見した場合に仲介手数料が発生するのか?
仲介手数料は、契約が成立した際に発生する成功報酬なので決まっていない以上発生はしませんし、内件で料金が発生することはまずありません。
礼金と仲介手数料は何が違うのか?
仲介手数料は不動産会社に対する成功報酬で、礼金は貸主に対して部屋を貸してくれてありがとうという、お礼の意味合いがあります。
礼金はお礼なので無料の所もあるが、仲介手数料は報酬なので無料のケースは少なく、値引き交渉もおすすめはしません。
まとめ
いかかでしたか?
賃貸の仲介手数料には、色々な仕組みがあり、多くの不動産は適切な仲介手数料で提示しています。
しかし、中には一部そうでない場合もありますので、この記事を参考にして頂ければ幸いです。